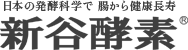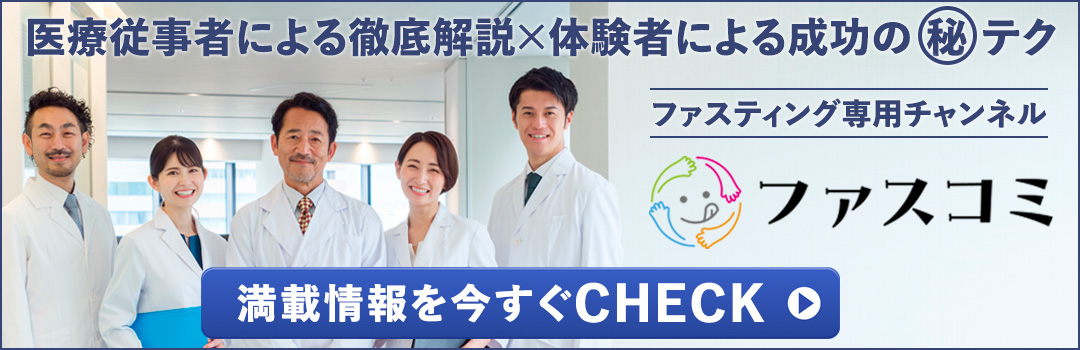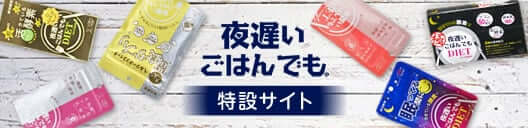「腸内フローラってよく聞くけれど、どのようにして整えれば良い?」
「腸内フローラにはどのような働きがあるの?」
このような疑問を抱いてしまう方は少なくありません。
私たちの健康的な毎日を過ごすために欠かせないのが腸内フローラです。
腸内フローラに存在する腸内細菌のバランスが悪いと、免疫力の低下や感染症・病気を招きかねません。
本記事では腸内フローラとは何かを説明し、腸内細菌の種類や改善方法を紹介します。
腸内フローラとは?
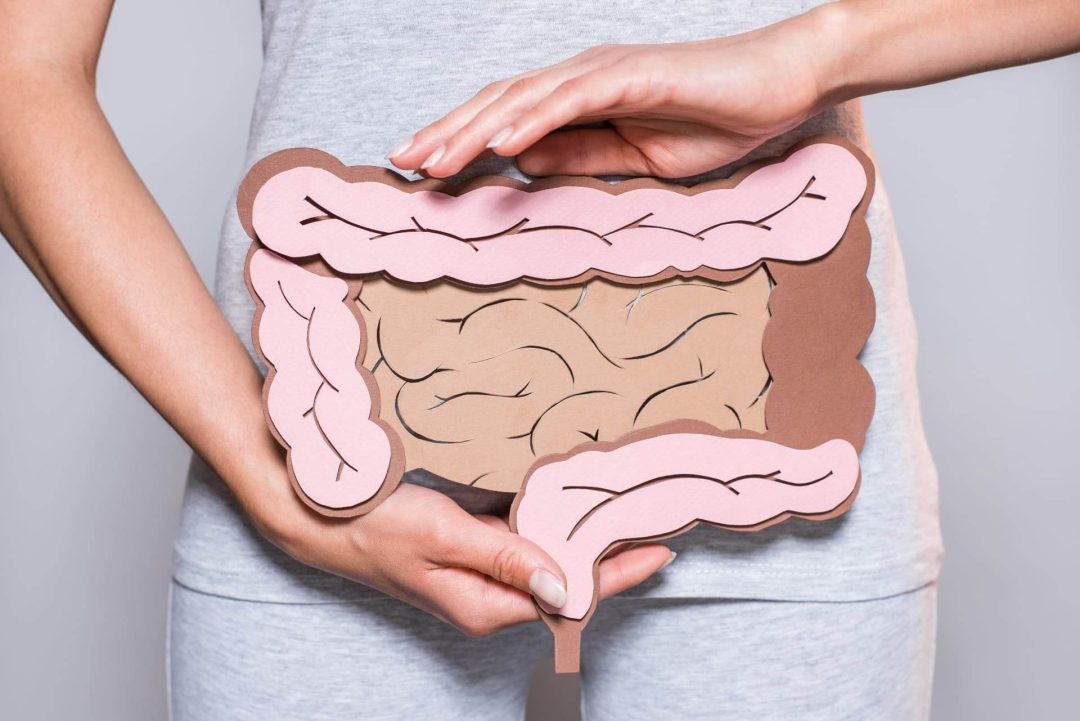
腸内フローラとは、「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」とも呼ばれ、腸内細菌が腸の壁に張り付いている様子を指します。
花畑によく似ていることから、英語で花畑を表す「フローラ(flora)」と呼ばれています。
健康を維持するうえで、腸内フローラの状態は非常に重要です。
腸内細菌のバランスが悪く、腸内フローラの状態が良くないと、免疫機能が低下してしまいます。
基本的に、腸内フローラのパターンは一生変わらないと言われています。
したがって、ふだんから「腸の調子が良くない」と感じる方は、食生活の見直しやサプリメントを使い、腸内フローラを整えることが大切です。
腸内フローラが整うとこんな効果がある
腸内フローラが整うと、健康面でさまざまな効果が期待できます。主な効果は以下の3つです。
- 腸内細菌はビタミンを作り出す
- 免疫細胞を刺激し免疫力を高める
- 人間が分解できない栄養も分解可能
腸内細菌はビタミンを作り出す
腸内フローラに存在する腸内細菌のなかには、ビタミンを作り出すものがあります。
産生されるビタミンは以下のとおりです。
- ビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビオチン、葉酸、ビタミンB12)
- ビタミンK
ビタミンB群には、代謝に必要な酵素の働きを補う役割があるとされています。
ビタミンKは血液の凝固や健康的な骨作りに役立つとされるビタミンです。
免疫細胞を刺激し免疫力を高める
腸内フローラのバランスが取れていると、免疫力の向上が見込めます。
腸内細菌の活動が活発化することで、腸内酵素が増えていくからです。
ウィルスや細菌と戦う免疫細胞は、約70%が腸に存在します。
その免疫細胞をより強くするものが腸内細菌です。
例えば腸内細菌の一つであるビフィズス菌は、有害な菌の繁殖を抑えて腸の働きを良くする役割を担っています。
また、ビフィズス菌SPやガセリ菌SPといった乳酸菌にはコレステロールを低下させる働きがあると言われています。
つまり、腸内フローラに善玉菌が多いと、さまざまな感染症や病気の予防につながるのです。
人間が分解できない栄養も分解可能
腸内細菌の合成・分解には、善玉菌が分泌する酵素が関わっています。
人間には分解できない「セルロース」という栄養素も、分解し、発酵させることができます。
腸内細菌は3種類
腸内細菌とは腸の内部に生息している細菌のことで、大きく分けて3種類あります。
- 善玉菌
- 悪玉菌
- 日和見菌(ひよりみきん)
ここではそれぞれについて詳しく解説します。
善玉菌
善玉菌は健康維持に貢献してくれる腸内細菌です。
主に次のような役割があります。
- 悪玉菌の増殖や定着を防ぎ、感染症を予防する
- 有害物質を体の外へ排出する手助けをする
- ビタミン(B1・B2・B6・B12・K・ニコチン酸・葉酸)を産生する
- 血清コレステロールを低下させる
このように、善玉菌は健康を維持するために重要な役割を果たしています。
また、3,000種類ものエンザイム(酵素)を作るともされており、健康な毎日を過ごすうえで欠かせないといえるでしょう。
関連記事:
日本人の善玉菌が増えるとどうなるのか。腸内バランスを整える方法とは
悪玉菌
悪玉菌は腸にとって悪い働きをする菌です。
たんぱく質や脂質が中心の食事を送ったり、不規則な生活を続けたりすることで増殖するとされています。
悪玉菌は腸の腐敗活動を起こします。。
つまり、悪玉菌優位な腸内フローラになってしまうと、腸の調子がどんどん悪くなっていく可能性があるでしょう。
もっとも、悪玉菌は不必要な存在ではありません。
タンパク質を分解し、便として処理し排泄するという役割があります。
大切なのは善玉菌と悪玉菌のバランスです。
日和見菌(ひよりみきん)
日和見菌は善玉菌と悪玉菌のどちらにも属さない菌で、腸内で優位な菌の働きを助けます。
具体的には、善玉菌が多いときには善玉菌の味方をし、悪玉菌が多いときには悪玉菌の働きを助けます。
腸内フローラの改善方法
健康に生きるうえで大切なのが、腸内フローラの改善です。
ここでは腸内フローラの改善方法を5つ紹介します。
- 善玉菌と悪玉菌のバランスを整える
- 善玉菌を増やし悪玉菌を抑える
- 酵素・食物繊維が豊富に含まれる食品を摂る
- 動物食を減らす
- 胃薬の服用を控える
善玉菌と悪玉菌のバランスを整える
善玉菌と悪玉菌のバランスを整え、双方の菌がきちんと働ける環境をつくりましょう。
理想的なバランスは「善玉菌:悪玉菌:日和見菌」が「2:1:7」になる状態です。
| 善玉菌 | 悪玉菌 | 日和見菌 | |
|---|---|---|---|
| 理想とされるバランス割合 | 2割 | 1割 | 7割 |
| 働き | 腸内を弱酸性に保つ | 腸内をアルカリ性にする | 善玉菌、悪玉菌のうち、優位な菌の働きをサポートする |
| 主な菌種 | 乳酸菌 ビフィズス菌など | 大腸菌(有毒株) ウェルシュ菌 ブドウ球菌など | バクテロイデス 大腸菌(無毒株) 連鎖球菌 |
大切なのは「悪玉菌より善玉菌の比率が上回ること」です。
善玉菌の割合が少なくなると日和見菌が悪玉菌を助けるようになり、腸の腐敗活動が進んでしまいます。
反対に、悪玉菌のほうが少なければ日和見菌が善玉菌をサポートするため、腸の調子が良くなるといえるでしょう。
善玉菌を増やして悪玉菌を抑える
理想的なバランスを整えるためには、善玉菌が住みやすい環境づくりを心がけましょう。
ここで重要なのが食事です。
特に次の食べ物や成分は、善玉菌を増やすうえでおすすめです。
- 発酵食品(納豆、こうじ、ヨーグルトなど)
- ビフィズス菌
- オリゴ糖
- 乳酸菌など
悪玉菌の増殖を抑えるためには、悪玉菌の好むタンパク質、高脂質の食事を控えることが大切です。
タンパク質や高脂質食品を過剰摂取すると、体に吸収されなかったタンパク質が悪玉菌によって有害物質に変えられてしまいます。
そのため、できるだけ肉類や油を抑えた食生活に改善しましょう。
また、ストレスの解消や運動も悪玉菌の増殖を抑えるうえで効果的です。
酵素・食物繊維が豊富に含まれる食品を摂る
日常的に酵素や食物繊維が豊富に含まれる食品を摂り入れるのも、腸内細菌のバランスを保つうえで重要です。食物繊維を豊富に含む主な食べ物は以下のとおりです。
- 穀類
- 芋
- 豆
- 海藻
- きのこ類など
食物繊維は、食べ物の中に含まれており、人の酵素では消化できない物質です。食物繊維は、水に溶ける「水溶性食物繊維」と水に溶けない「不溶性食物繊維」に大別されます。水溶性食物繊維は、食後の急激な血糖上昇を防いだり、胆汁酸・コレステロールなどを排出したり、腸を整える働きがあります。また、不溶性食物繊維は、便秘の改善や、腸の蠕動運動を活発にさせるなどの効果があります。
また、食物繊維とともに酵素を摂ることも意識しましょう。
新谷弘実医学博士によると、良い胃相・腸相をしている人たちに共通しているのは、酵素をたくさん含むフレッシュな食物を多く摂っていることです。
酵素を摂り入れるためには、「酵素の補給に役立つか」、「酵素の働きを助けるか」、「酵素を消耗しないか」の3つのポイントで食べ物を選びましょう。
酵素を多く含む食べ物は生きている食べ物です。
野菜でも穀物でも、できるだけ生きているもの、新鮮なものを選びましょう。
健康な生活を送っている人の酵素の保有量が多いように、フレッシュであればあるほど酵素が多く含まれているとされています。
ただし、豆や穀物は生食できませんので、必ず火を通すように注意してください。
動物食を減らす
豚や牛、鶏の肉ばかりの食生活はあまりおすすめしません。
飽和脂肪酸が含まれ、不飽和脂肪酸が少ない(含まれない)からです。
飽和脂肪酸の過剰摂取は、脂質異常症のリスクや血液中のLDLコレステロールが増加する可能性があります。
豚や牛、鶏の代わりとしておすすめな食べ物が魚です。
魚に含まれているのは不飽和脂肪酸であるため、動物食より飽和脂肪酸の摂取を抑えることができます。
まとめ

腸内フローラを改善するためには、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という腸内細菌のバランスが大切です。
バランスが崩れてしまうと、さまざまな健康被害につながりかねません。
また、腸内細菌は酵素を作り出します。
酵素は外部から摂取するだけではなく、腸内細菌が活発に働くような腸内環境を作ることも重要です。
ぜひ本記事で紹介したとおり、酵素を多く含んだ食生活を心がけてください。
【参考文献・参考URL】
新谷弘実(2005)「病気にならない生き方」サンマーク出版
新谷弘実(2008)「図解 病気にならない生き方」サンマーク出版
厚生労働省 e-ヘルスネット|腸内細菌と健康
厚生労働省 e-ヘルスネット|ビフィズス菌
厚生労働省 e-ヘルスネット|乳酸菌(にゅうさんきん)